第四話 皇帝光臨(3)
その後のティンタ郡一帯の集落は激しい興奮に包まれたまま、人々はまるで蜂の巣をつついたかのように慌しく動き回っていた。
インカ族の者たちは当然のことながら、混血児の者たち、そして、当地生まれのスペイン人たちまでもが、明朝の出陣に向けての準備を嬉々として開始した。
そして、一見、いつもと変わらぬ仕事に勤(いそ)しむ黒人の者たちの横顔にさえ、密かな高揚が滲んでいた。
スペイン人の圧政によって苦しんできたのは、決してインカ族の者たちだけではなかった。
当地生まれのスペイン人も混血児たちも、そして、はるばるアフリカより白人に連れてこられた黒人奴隷たちも、スペイン渡来の白人たちによって激しく蔑視され、搾取され続けてきた不平分子であった。
トゥパク・アマルは、もともとそれらの人々の窮状にも目を向けていたし、この反乱においても、単にインカ族の解放にとどまらず、それらの人々の真の自由を取り戻すことをも反乱計画当初からその眼目としていた。
ところで、このインカ軍の構成の特徴の一つには、多くの女性も参加したということが挙げられる。
実際、アンデスの女性たちは、織物や土器を作り家事を取り仕切るばかりか、身体的にも精神的にも強靭で、しばしば畜群を追って遠く旅をすることもあるし、また、農作業などにおいても、平素から男性顔負けの働きぶりを示す。
歴史上の資料に残る反乱軍の隊長たちの中には、実際に、複数の女性たちの名を見出すことができる。
そんな集落の喧騒の中を、人々の波をかきわけるようにしながらコイユールは自分の住む小屋への帰路を急いだ。
中央広場から集落のはずれにある彼女の小屋までは、軽く見積もっても1時間以上の距離があった。
集落の中心部を抜けるとき、教会の傍のアンドレスの館の前を通りかかる。
無意識のうちに、コイユールの足が、ふっと止まる。
門の傍でその美しい西洋建築をそっと見上げると、不意に自分の名を呼ぶ、あの少年の日のアンドレスの声が聞こえてくる気がする。
胸の前で握り締める彼女の手が、微かに震えた。
コイユールは揺れる瞳で、今は灯りもともっていないニ階のアンドレスの部屋の窓を見つめた。

かつて二人で語り合った日々が、あまりにも懐かしく、切なく思い出され、彼女の胸をそっと締めつける。
その思いを振り払うようにして、コイユールは小屋への道を走りはじめた。
コイユールが、自分の小屋のある集落はずれに戻ってくる頃には、すっかり日も傾きかけていた。
前方の空にはそろそろ寝座(ねぐら)に戻るのだろうか、黒い影のような一羽のコンドルが、山脈の方へと滑るように飛び去っていくのが見える。
その瞬間、彼女の脳裏に、あの広場で見たトゥパク・アマルの姿が、その声が、その言葉が、ありありと甦ってきた。
『誇り高き、気高き魂が、今も、そなたたち一人一人の中に生きていることに、目覚めよ!!
今こそ、眠れる魂を呼び覚まそうではないか!!
そして、我々自身の手で、このインカの地を、この地の民を、己(おのれ)自身を解放するのだ!!』
コイユールは、再び胸の前で両手を祈るように硬く結び合わせた。
「トゥパク・アマル様…」
彼方へ飛び去るコンドルを見つめる彼女の瞳の中にも、静かな炎が燃え上がる。
『たとえ皇帝陛下が生きていたとしても、スペイン人から闘って勝ち取らなければ、この国はインカの人々の手には決して戻ってこない!』
ずっと昔、アンドレスがそう語った言葉通り、今、まさにそれが動き出そうとしているのだ。
涼やかで清い、そのくっきりとした目元に、澄んだ光が宿りはじめる。
(私たち自身で、私たちを解放する…!!)
胸が熱くなり、鼓動が速くなる。
明日、進軍と…、明朝、結集と、言っていた。
コイユールは夜の帳がおりはじめた農道の片隅で、立ち止まったまま空を見つめ続ける。

しかし、その目には、もはや空の風景は映っていなかった。
彼女は、ただ、じっと自分の心の中を見つめていた。
自らの中に静かに燃え続けてきた炎。
その炎が、今、さらに激しく、強く、燃え上がっている。
そう、この日が来るのをずっと待っていたのかもしれない。
アンドレスに出会い、そして、トゥパク・アマル様に出会った時から。
きっと、もう何年も前に、あのビラコチャの神殿で、偶然にもトゥパク・アマル様を垣間見たあの日から…――!
私たち自身で、私たちを解放するのだと、トゥパク・アマル様は言っていた。
そのために、私たち一人一人の力が必要なのだ、と。
コイユールは思いつめたような眼差しで、再び空を見た。
既に、あたりは闇に包まれ、晩春の涼風が吹きぬけていく。
風の揺らす新緑の草木が、ざわめく音がする。
長大なコルディエラ山脈に囲まれた空には、次第に初夏の星座が瞬きはじめる。
そして、それを見上げるコイユールの瞳にも、煌く星々がくっきりと映し出されていた。
しかし、ただ一つ、コイユールをトゥパク・アマルらの軍に加わることを思い留まらせるものがあった。
それは、祖母のことだった。
ただでさえ最近はめっきり老けこみ弱ってきている祖母を、これからますます政情不安に陥りそうな当地に一人残していくことは、非常に心配なことであった。
これまで親代わりとなり自分を育ててきてくれた祖母に、言葉では言い尽くせぬ深い恩を感じてもいた。
それに、多くの人々が参戦するために集落を離れれば、農地を耕す者も減ってしまうだろう。
残った女性や年寄りで、この地を守っていかねばならぬのだ。
それはそれで、戦闘に加わることにも等しい難儀なことに相違ない。
コイユールは、どのような気持ちで、どのような顔で、祖母の待つ小屋に戻ったらよいのか決められず、まだ農道の端に立ち尽くしたままでいた。
吹き抜ける夜風の冷たさが増している。
冷え切った体を腕で抱くようにしながら、彼女は心の中で無意識のうちに呼びかける。
(アンドレス!
私、どうしたらいい…?)
そして、アンドレスもまた、トゥパク・アマルの館の広間の窓から、一人、風の吹きぬける戸外を見ていた。
すっかり夜の帳がおりた広大な庭の随所では、松明の炎が風に煽られ、上空に舞い上がっては夜闇を焦がしている。
館には、まもなくトゥパク・アマルの有力な同盟者の一人、インカ族の豪族オルティゴーサが到着する予定になっている。
それを待つほんの束の間だったが、トゥパク・アマルら館の者たちは、ひとときの一人の時間をそれぞれに過ごしていた。
トゥパク・アマルも、今は書斎に一人で入っている。
アンドレスは、窓の向こうのはるか集落の彼方まで、遠く視線を向けた。
それは、コイユールの家のある方角だった。
アンドレスの瞳が微かに揺れる。
コイユールのことだ、きっと、あの広場に来ていたに相違ない…。
どう感じ、そして、今、一体、何を思っているのだろうか。

窓辺に添えられたアンドレスの指に、力がこもる。
馬を走らせれば、ここから30分もかからぬ距離にいるのだ。
今まではアリアガを見張っていたが、今なら…――!
アンドレスは思い切ったように、足早に戸口に向かいはじめた。
それをすかさず、トゥパク・アマルの腹心ビルカパサが制する。
「アンドレス様、どこに行かれます?」
アンドレスを見るビルカパサの目は、完璧なまでに感情の統制がなされており、決して冷たいわけではないのだが、目的遂行以外の情の挟む余地を全く与えぬ色である。
「まもなく、オルティゴーサ様がお着きになられます。
今暫く、お待ちを」
まるで己の心を見透かすようなビルカパサの視線を、アンドレスは思わずそらす。
「すぐに戻ります」
アンドレスの不可解な挙動にビルカパサはいっそう見据えるような眼差しで、「ならば、どこに行かれるのか教えてください。トゥパク・アマル様にお伝えしておきます」と、婉曲的に牽制してくる。
アンドレスは、ぐっと言葉に詰まる。
アンドレスが返す言葉を探しているうちに、今度は、背後から明るい子どもたちの声が響く。
「アンドレス!
アンドレス!!」
振り返ると、トゥパク・アマルの子どもたちが瞳を輝かせながら、やっとつかまえたとばかりに、アンドレスの方に駆け寄ってくるところだった。
トゥパク・アマルには、先に登場した末子のフェルナンドのほか、長男のイポーリト、次男のマリアノがいる。
それぞれ、現在、イポーリトが12歳、マリアノが10歳、そして、フェルナンドが8歳になったばかりである。
三人共、トゥパク・アマル似の、流れるような黒髪と澄んだ美しい切れ長の目をした、凛々しくも、天使のように愛らしい少年たちだった。
たちまち、まだ幼いフェルナンドは何の躊躇もなく弾丸のように飛んできて、アンドレスの足に巻きつくと、ニコニコした笑顔でまっすぐに見上げてくる。
すぐにイポーリトとマリアノもアンドレスを囲むようにして、「ねえ、アンドレス、お願いがあるのだけど」と、まだあどけなさの残る、はにかむような輝く瞳を向けてくる。
アンドレスは、ドアの方に進みかけていた足を止めるしかなかった。
ビルカパサが、静かな眼差しで見守っている。
アンドレスは少年たちの目の高さに跪き、「願いとは、何ですか?」と、いつもの優しい眼差しで三人を交互に見渡した。
イポーリトが瞳できちんとアンドレスに礼を払い、「アンドレスがもっている、あのサーベルを見せてほしいのだけれど」と、長男らしく三人を代表して、トゥパク・アマルそっくりの美しいケチュア語で話す。
残りの二人も頷きながら、強い期待感を込めた眼差しをまっすぐに向けてくる。
アンドレスは戸外の方に思いを残しながらも、しっかりと三人の少年たちに囲まれて観念したように頷く。
「わかりました。おいでください」と、広間の一隅の壁に大切そうに立て掛けていたサーベルの方に三人をいざなった。
見えやすいように三人の中央にサーベルを置くと、少年たちは恍惚とした表情で喰い入るように見入る。

長男のイポーリトが、眩しそうな目をして、思わず溜息を漏らした。
「なんて綺麗で強そうな剣なのだろう…!
父上だって、こんなにすごい剣は持っていないのに」
他の二人も幾度も頷きながら、次男のマリアノが利発そうな瞳をアンドレスに向ける。
「アンドレス、このサーベルは、どこで手にいれたの?」
アンドレスは優しい眼差しで応える。
「俺に武術を教えてくださった方から戴(いただい)たのです」
不意にアパサのことが思い出され、熱いものがこみあげる。
その時、サーベルを囲む四人の若者たちの輪の中に、いつの間にか広間に戻っていたトゥパク・アマルがすっと入ってきた。
サーベルを前にして、子どもたちの目の高さに合わせて跪いているアンドレスの隣の床に、トゥパク・アマルも共に跪く。
「父上!!」
少年たちが、嬉しそうな声を上げた。
トゥパク・アマルは息子たちに微笑み返してから、自らも輝くような瞳で、そのサーベルを見つめた。
「確かに、見事なサーベルだ。
これはアパサ殿から?」
アンドレスはしっかりと頷きながら、「はい」と力強く応える。
「アパサ殿は、厳しい師であったろう」
トゥパク・アマルは静かな笑みを湛えた眼差しで、アンドレスを見る。
アンドレスは再び「はい」と応え、それから、「そして、本当に素晴らしい師でした」と、トゥパク・アマルの目に深く礼を払った。
「アパサ殿の元に行かせて頂けたこと、生涯無二の宝と感じます」
アンドレスの言葉に、トゥパク・アマルはその目を細め、無言のまま、ゆっくり深く頷いた。
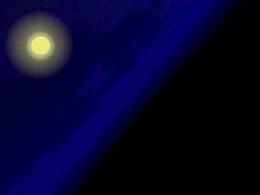
その後、間もなくオルティゴーサが到着した。
オルティゴーサはインカ族の豪族で、トゥパク・アマルらの治めるティンタ郡に比較的近いアコビア郡のカシーケ(領主)であった。
トゥパク・アマルにとって、かのアパサ同様、最も有力な同盟者の一人である。
夜闇の中を勢い良く馬で馳せ参じたその男は、トゥパク・アマルの従弟ディエゴをも凌ぐ筋骨逞しい大男で、厳(いかめ)しい褐色の顔には、耳から顎一帯にかけて黒々とした髭をたっぷりと蓄えている。
全身からは強い気迫が漲り、いかにも戦場の似合いそうな武人という風貌だ。
出迎えたトゥパク・アマルとオルティゴーサは、共にがっちりと手を握り合った。
「トゥパク・アマル様、いよいよですな!!」
オルティゴーサが逞しい肩をいからせながら、興奮をかくせぬ様子で、太く、響く声で言う。
「ああ、いよいよだ」
トゥパク・アマルも力強く頷き返した。
それから、トゥパク・アマルを中心に、オルティゴーサ、従弟ディエゴ、腹心ビルカパサ、義兄弟フランシスコ、相談役ベルムデス、甥のアンドレス、そして、妻のミカエラが参加し、明日からの行軍に向けて最終的な打ち合わせが行われた。
「兵の状態は、明朝の出陣に向けて万全ですぞ!!」
オルティゴーサはトゥパク・アマルの方にその身を乗り出すようにして、武人としての自信溢れる堂々たる声で言った。
トゥパク・アマルも、しかと頷き返す。
スペイン人の役人の嫌疑の目を逃れるため、トゥパク・アマルは敢えて自分のもとではなく、このオルティゴーサのもとに武勇に秀でた者たちを集め、専門兵として密かに訓練を行わせてきた。
オルティゴーサは、アンドレスの師であるアパサ同様、ペルー副王領の中では名の轟く腕の優れた武人であり、有能な戦術家でもあった。
この後、反乱本部の参謀として機能していくことになる男である。
燭台の下に広げた地勢図を前にして、トゥパク・アマルは力のこもった眼差しで集まった者たちを見渡した。
「本陣をここトゥンガスカに置き、まず、キスピカンチ郡の首府キキハナに向かって進軍を開始する」
一同も深く頷く。
キスピカンチ郡はトゥパク・アマルらの治めるティンタ郡に隣接する郡であり、その地の代官は亡き当地の代官アリアガと結託して、永年に渡り当地に類する非道な搾取を続けていた。
いまや、迅速な行動によって極悪非道なスペイン人の役人たちを屠り、スペインの植民地支配の絆を断ち切り、一気にその瓦解を引き起こさねばならぬ…――!!
それぞれの者たちの表情に、険しい緊張と気迫が漲っていた。

さらに、出陣までのこの短期間に、トゥパク・アマルがしなければならぬことは多かった。
彼は予め反乱計画の根回しをしておいた諸郡の有力なカシーケ(首領)たちに早急に使者を送り、いよいよ反乱の火蓋が切られたことを告知した。
そして、各地において機を逸せずに蜂起し、代官を逮捕し、代官の職能を廃絶し、強制売付けや強制労働その他の非道な搾取を直ちに廃止に導くべく通告した。
もちろん、使者は、ラ・プラタ副王領の同盟者、あのアパサの元にも走った。
どれほど早急に使者を飛ばしても、交通手段が徒歩か、せいぜい馬かラバしかないこの時代、遠方の同盟者までトゥパク・アマルの言葉が届くには、何日間もの期間が必要だった。
一方で、トゥパク・アマルは、首府リマにも、そして、遠からず奪還せねばならぬ牙城クスコ――かつてのインカ帝国の首都である――にも、反乱の実情に関する情報が漏洩せぬよう、厳重な配慮を怠らなかった。
スペイン側の中枢部がこの反乱を知れば、すぐさま大量の火器を投入した討伐軍を組織し、躍起となってインカ軍の制圧に向かってくることは必定。
スペイン側の役人に気付かれる前に、いかにインカ軍の勢力を高められるかは、今後の命運を分ける重要な鍵となる。
先述の通り、通信手段はスペイン側にとっても、せいぜい使者による手紙か口頭による伝達しかなく、つまりは足だけが通信の道具であったこの時代においては、その通行路を押さえてしまうことが肝要だった。
そこで、トゥパク・アマルは、今後、反乱軍及び同盟者たちが押さえる地域には、通行許可証が無ければ通行出来ぬよう整備するように、各同盟者たちに指令を発した。
こうして、交通の要所を押さえ、銃後の守りを厳しく固めるべく采配を振るった。
なお、有能かつ勇猛な同志でもある妻ミカエラには、トゥパク・アマルらが前線で戦っている間、この本陣トゥンガスカにて、武器・食糧の管理及び補給を指揮するよう指示がなされた。
もちろん、ミカエラは、本来の男勝りの才覚を存分に発揮すべく、重責を伴うその要請に、麗しくも凛々しい眼差しでしかと同意した。
一方、その頃、コイユールは、やはり考えがまとまらぬまま、それでも、ともかくも小屋に戻り、祖母のために夕食の支度をすませた。
今日も昨日も、足腰の弱った祖母は、広場には出向いていなかった。
しかし、昨日からの広場でのトゥパク・アマルの一連の動向については、すっかり村中の噂になっていたから、事態のおおよその成り行きは祖母も知っていた。
だが、そのことには、祖母もコイユールも何も触れずに過ごしていた。
そして、今、やはり、そのことには触れられぬまま、窓もない薄暗い小さな一間の小屋の片隅で、いつものように質素な食卓を祖母と囲んでいる。
蝋の少なくなった小さな一本の蝋燭の向こうで、皺だらけになった顎のあたりを一生懸命動かしながら、湯で柔らかくした干したジャガイモの切片を歯茎で噛んでいる祖母を見る。
皿の傍に力なく添えられた枯れ枝のように痩せ細った、その祖母の指や腕が痛々しい。
そんな祖母を前にして、自分がこの家を出てインカ軍に加わりたいなどとは、コイユールにはとても言えなかった。
己の方に注がれる苦し気なコイユールの視線に、もう随分前から気付いていたように、しかし、まずは慎重にジャガイモを喉に流し込んでから、ゆっくりと老婆は顔を上げた。
突然目が合って、コイユールの鼓動が速まる。
老婆は皺だらけの目元に笑みを浮かべた。
そして、少し探るような眼差しになって、コイユールの瞳を覗く。
コイユールは、どんな色を浮かべたらいいのか戸惑いつつ、小さく笑い返した。
すると、ふっと老婆の眼差しに、いたずらっぽい色が浮んだ。
意外な老婆の眼差しに、コイユールは目を瞬かせ、「おばあちゃん?」と、思わず問いかける。
「おまえ、まさか、わたしのために、ここに残ろうなんて考えているんじゃあ、あるまいね?」
老婆は、いたずらっぽい微笑みを湛えたまま、しかし、探るようにコイユールの顔を覗いてくる。
不意の言葉に、コイユールの手から、もうすっかり錆付いたスプーンがこぼれ、小さな音を立てて皿の上に落ちた。
コイユールは、目を見開いて、祖母の顔を驚いたように見つめる。
老婆は相変わらず、いたずらっぽい笑みを浮かべたまま、コイユールの瞳に応えるように言う。
「おまえは、誇り高いインカの娘だろう。
今、皇帝様を助けないでどうするんだい」
わざと大袈裟な表情をつくってみせる祖母に、コイユールの胸が熱くなった。
「おばあちゃん…!」
コイユールは、身を乗り出すようにして、祖母を見据えた。
老婆は皺だらけの顔に満面の笑みを浮かべて、何度も頷いている。
「わたしの事なら、心配しなくていいんだよ。
自分のことくらい、自分でできるさ。
それより、おまえは皇帝様と力を合わせて、はやくこのひどい生活を何とかしておくれ」
相変わらず、おどけたように言う祖母の口調に、自分の不安を取り去ろうとしてくれているのだという祖母の思いが伝わってきて、コイユールの心はいっそう切なくなった。
コイユールの揺れる瞳から、思わず涙がこぼれそうになっている。
祖母は、優しい眼差しになって、コイユールの髪にそっと触れた。
「コイユール。
おまえは、おまえが生きたいように生きておくれ」
老婆の目にも、うっすらと涙が滲む。
そして、再び、おどけたような口調で、「わたしがもう少し若かったら、一番乗りで、皇帝様のところに馳せ参じているところなんだけどねえ」と言って、笑った。
『おばあちゃん、本当にいいの?!行っても、いいの?!』と、尋ね返しそうになる自分をぐっと抑えて、コイユールはその言葉を呑みこんだ。
そんなふうに聞いたら、祖母はまた気持ちをこらえて、大丈夫というだけだと分かっていた。
それに、そんなふうに尋ねてしまったら、祖母に決断を委ねるのに等しいことになってしまう。
これは、自分自身が、決断すべき問題なのだ…――!!
コイユールは、涙を浮かべながらも、意を決した瞳で祖母を見つめた。
私は皇帝様と一緒に行きますと、コイユールの目に浮んだ決意の色に、老婆もまっすぐな目で頷いた。
コイユールの瞳から、涙が一筋、頬を伝う。
「おばあちゃん、本当に…、どうもありがとう」
今回のことも、そして、今まで育ててくれたことも…――。
コイユールは、涙の溢れる瞳で深く礼を払った。
祖母も目を細め、優しくコイユールの髪を撫でたまま幾度も頷く。
霞んだ視界の中で、いつの間にか、とても真剣な眼差しに変わっている祖母は、揺れるような瞳でじっとコイユールを見つめた。
「命だけは、大事にね、コイユール」
コイユールは深く頷いた。
「おばあちゃんも…」
祖母も深く頷いた。
いつの間にか、老婆の目からも涙が伝う。
また必ず戻っておいで、とも、また必ず帰ってくる、とも二人は言葉にすることはできなかった。
もう二度と会えないかもしれない…。
コイユールも祖母も、この時、心の奥でそっと覚悟を決めたのだった。



